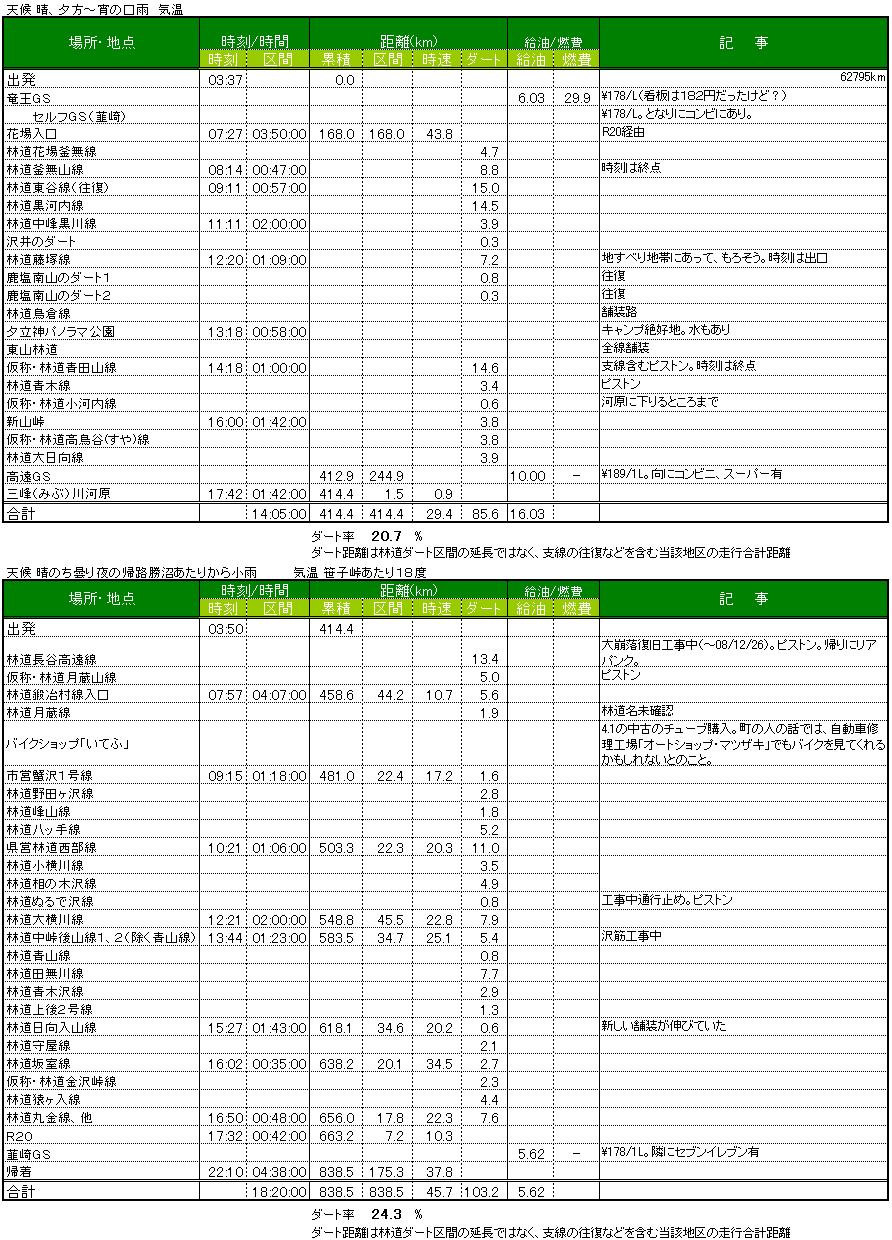|
1日目 林道釜無山線の出口で富士見町の希少植物保護監視員の方と話をした。希少植物となったアツモリソウの保護活動をやっているとのこと。花場釜無線〜釜無山線一体がその対象になっている。以前はどこにでも生えていたらしいが、林業資源開発のため行われた唐松の植林で急速に生態が破壊されたらしい。大雨などで土砂が流れ出すと、日当たりのよいところではよく芽を出したりすると言う。 山のこと、釣りのことなど色々話をうかがうことができた。いわく、 ・唐松の山に熊はいない(餌が無い)が広葉樹の山にはいる可能性がある。 ・唐松はまっすぐ立ってはいるが、製材するとよじれて使えない。防止加工をすると、使用できるようになるが、高くなって競争力が失われる。 ・山女、あまごはまづめだが、岩魚は水温の十分上がる好天時の真昼間でなければ食わない。 ・山室川は釣りによい。 ・キャッチ&リリースはしてはならない。どうしてもするなら、魚には触らないこと(これは自分も大賛成。キャッチ&リリースをするくらいなら釣りはしない)。 ・諏訪湖も外来魚種(ブラックバスなど)で大きな問題となっている。 などなど。 東谷線にも入ってみる。ネットでは抜けられるとの情報もあったが、黒河内線側は橋の先で堅固なゲートがあり、稜線まで引き返す。迂回して黒河内線を下りながら出口をチェックし帰宅後調べた結果黒河内支線から脱出できそうなことがわかった。次回の課題である。 黒河内線を出て、いっきに大鹿村まで南下する。途中にも数々のすばらしい林道があるが、今回は未走の林道を優先する。 中峰黒川線はかなり以前に走ったことがある。そのときは雨模様で白いガスの中を走った記憶しかない。ダートは上部に4キロ足らずしか残っておらず、前後の長い舗装区間を考えると意欲もなえがちになるが、緑なす黒川牧場の眺めは美しかった。 藤塚線は小塩側が地すべり地帯になっていて、傾斜が強くとてももろそうだ。殺伐とした感がぬぐえない。 鹿塩は登山をやっていたころ、伊那大島からバスに揺られには何度もきたことのある場所だ。次にきたときには、そのときのように塩川まで入ってみたい。鹿塩から鳥倉線に入ってみたが、これといったダートは発見できず、夕立神パノラマ公園まで行って引き返す。東山線から大河原に下り、小渋川をはさんだ対岸の青田山方面に上がってみた。北の原の上からダートになっているが、いずれもピストン林道である。青田山と栂村山の鞍部では4人ほどの人が車で来てキャンプをしており驚いた。青木川沿いも調べる予定であったが、徒労に終わりそうな気がしたので省略し折草峠にむけ北上する。 高森山線の当初計画のの起点(終点?)であったと思われる塩沢橋から沢沿いに入ってみたが、ヤブのダートしかなかったのですぐに引き返す。 四徳手前から中組陣馬林道方面に上がる道は見つけることができなかった。小河内川沿いの林道はピストンとわかっていたので、入ってすぐのキャンプ好適地を確認しただけで引き返す。 折草峠の下りにかかると路面がぬれており、霧雨が降っている。夕立がらみなら早く山を下りたいので、桃平周辺の未調査ダートは割愛して先を急ぐ。 新山峠から高鳥谷山へ向かう。このあたりは降っていないので、予定のルートを経て高遠へ。2本のダートは走行することはできたが、茸山のため、ゲート規制されているところも多く残念だ。このあたりまだ調査が必要だ。 高遠で食料を仕入れ、三峰川の河原にテントを張る。今回は、フライシート、床面防水用のブルーシートも持ってこなかったのに、日暮れ時から雨が降り出し、まいった。ぬれた背中が寒く、夜が長かった。 2日目 今日の行程には余裕があるが、いつもの習慣から夜明け前に出発する。 長谷高遠線は、起点に工事通行止めの看板が無かったのでもしやと思ったが、やはりまだ復旧工事中であった。工事期間が年内一杯ということなので、来年には馬越までの区間は走れるようになるのだろうか。 起点まで戻り、一時停車して右折しようとしたらリアが「ぐにゃり」と言う感じで流れた。パンクだア・・・。そう言えば、戻ってくる途中のダートで「ボスッ」と言う音がして何かなあと思っていたが、ビードが落ちなかったので気がつかなかった。 かなり大きな穴が接地面中央からリム側まで貫通している。特にリム側はかぎ裂き状に破れているため、修理不能に思われた。持っているフロントチューブを入れようかとも思ったが、それで今日一日走れるとも思えない。それならダメもとでとにかくパッチを張り、バイク屋さんを探してチューブを入手することにした。タイヤが加熱しないように空気圧は標準より心持ち高くする。 まず、散歩中の人に教えてもらったバイク屋さんの位置を確認する。リアタイヤの状態を頻繁に確認するが、信じがたいことにタイヤの空気が全然抜けてこない。開店の9時まで時間があるので、予定していた近くの林道の探索を続けることにした。 鍛冶村線は、四輪のわだちの部分のみに砂利が露出した緑の美しい林道だ。道なりに進むと、すぐに廃道になってしまっているところがあるが、ここは左に鋭角に切りあがっていく分岐路がただしいルート。月蔵山から伸びる稜線を大きく迂回して、やがて町道高峰線に接続する。ここまでリアをかばいながら恐る恐る走ってきたが、まだ大丈夫のようだ。 バイク屋さんではちょうどのサイズはなかったが、ひとつ小さいサイズの中古のチューブを見つけてもらい、助かった。 予定通り峰山線に向かい、支線の八ッ手線を探索する。前回間違えて隣の中樽線(舗装)に行ってしまい???のままだったが、これで解決した。ここはやや荒れており、登りにとった方が楽しそうだ。 八ッ手線を降りて、辰野に向かう。以前より気にはなっていたがやや離れているので、今まで行く機会がなかったのだった。西部線のルートは地図上今ひとつよくわからなかったが、結局小横川まで完抜していた(今村線接続点〜小横川間が08/08/27まで開設工事中だが道路はすでにつながっていた)。当初計画では西部線は大横川線までの予定であったが、小横川までに計画縮小されたものだ。 大横川線はかたくりの里の裏手から始まっているが、それと思しきところは電気柵が設置してある。仕方なく反対側から入るつもりで、横川の奥へ進む。横川坊主線は起点(蛇石キャンプ場)のところで09/03/12まで工事通行止めであった。戻って、大横川線を終点から入り、出口まで来てみるとやはり先ほどのところである。一瞬引き返しかと思ったが、よく見ると開閉式になっている。こんなところは何度も通っているのに、なぜ先ほど気がつかなかったのか。 依然としてタイヤは大丈夫だが、念のため細かい支線の探索は中止して次回の課題とした。 もみじ湖を経て諏訪湖南の峠を巡る林道に向かう。 中峠後山線は名称からすると中峠と後山を結ぶ路線であるが、中間に青山線をはさんでいてなんとも不思議な路線だ。中峠から下る沢筋の復旧工事中で通行止めになっている。隣の南峠を越える田無川線は、高速道路と並行するたりで諏訪湖を望むことができる。ここも支線の探索は割愛した。 青木沢線、上後2号線は事前調査では知らなかったところだが、ひっそりとした感じがよい。もっとダートがありそうな気がしたが、持参した地図の切れ目がちょうどこのあたりだったので、ここも次回の課題とする。 日向入山線は、さらに新しい舗装が延びてダートはもう600mほどしか残っていない。ここは生活道路的な要素もあるのでやむをえないことか。 杖突峠から守屋線をまわり坂室線を下る。途中で分岐する旧道のダートは荒れ気味である。金沢峠への道は以前から荒れていたが、今回はさらにそれが進み、部分的には甲子林道なみになっている。峠で休んでいると、軽トラが全く躊躇せずこのダートに入っていった。地元の人はカブや軽トラで恐るべき走破能力を示すので心配は要らないかもしれないが、慣れていなければ確実にスタックだろう。 猿ヶ入線を経て、今回最後の林道となる丸金線を下る。ここもクレバスが発達し結構荒れている。途中たまらず道脇の熊笹側にルートを取ったら笹の下が切り立っていて、ハンドルを切れずそのままフロントから転倒。あと数キロで今日は終わりなのに、左半身は泥まみれ・・・。ボテゴケはしょっちゅうだが走っていて転んだのは久しぶりだ。 昨日に続いてまだ十分明るいうちの早仕舞いだが、タイヤの件もあるので帰路につく。途中から降り出した雨、雨量はたいしたことはなかったが長時間降られていたため帰宅するころにはずぶぬれになった。寒くて震えていたが、大穴のあいたチューブが400kmも持ってくれた幸運に感謝しよう(後日記:帰宅後10日位で完全に空気が抜けた)。 ところで、高遠のバイク屋で買った中古のチューブ、帰宅後荷物の中を探したがなぜかどこにも無い(?_?)。もしや、知らぬ間に穴の開いたチューブと入れ替わっていた、などということはあるまいな・・・。 |